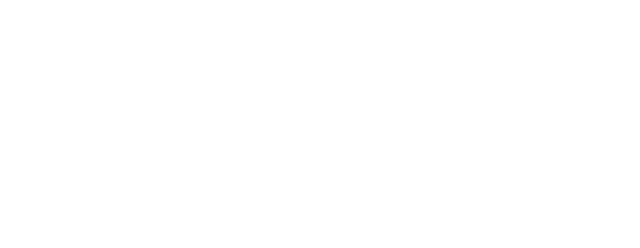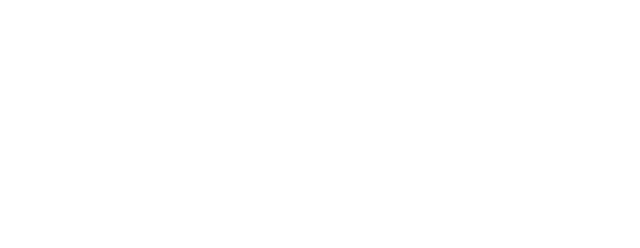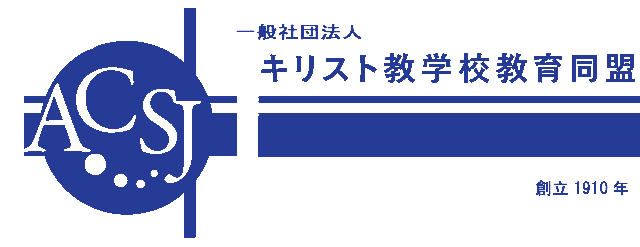キリスト教学校教育バックナンバー
第4回キリスト教女子大学・短期大学学長協議会
女性大学の存在意味を問う
坂本 辰朗
国際比較からみた日本の女性高等教育
日本の女性高等教育は国際比較から見て、危機的な状況にあると言えましょう。OECDの最新の調査報告(2003年9月)によれば、加盟国26カ国の、学士課程卒業者に占める女性の比率の平均は55%です。つまり、OECD加盟国全体の趨勢としては、学士課程教育の修了者は女性が多数派ということになります。ただし日本は、26カ国中最低の39%です。
この事実は、日本の女性高等教育にとっては厳しいものでしょう。唯一の救いは、女性の進学者の増大傾向――高等教育進学者のプールそのものは減少してゆく中、唯一、増加が見込まれるのが女性の進学者であるということ――です。だがしかし、そうであればこそなおさら、女性が入学する大学・短大において、女性にとってどれほど善い学習経験が用意されるのかどうかが、ますます重要で危急の問題になったと言えないでしょうか。
女性のみの学習環境の重要性
では、現在、日米共に女性の高等教育の主要な形式になっている男女共学制は、このような女性高等教育の期待に応えるものであるのでしょうか。
現在のアメリカ合衆国の四年制女性大学は64校で学生数は約13万人、全米の学生数に占める割合は1%に満たない少数勢力となっています。かつて1960年に176校あったのと比べると、大幅に縮小したことになります。日本の場合も同様で、四年制女性大学が約90校で、全四年制大学の14%を占めるに過ぎません。特に、この5年間ほどで共学に転換した女性大学は、四年制と二年制を合わせると二桁の数になり、これは、1970年代初頭のアメリカ合衆国の状況を彷彿とさせるものです。
しかしながら、アメリカ合衆国においては、1990年代以降、女性大学は一つのブームになりました。これは、女性大学出身の女性の活躍が目立つこと――たとえば、ヒラリー・クリントン上院議員の母校は東部の名門女性大学ウエルズレイです――もありますが、近年の研究が、高等教育における男女共学制度は、女性にとって必ずしも最善の教育制度ではないことを、さらに、女性にのみの学習環境がもつ意義について再評価をおこなったことが、その理由として挙げられましょう。
女性アチーヴァー研究
たとえば、ティッドボール教授らによって書かれた一連の論文は、後に、「女性アチーヴァー研究」と呼ばれるようになりますが、女性大学の新たな存在意義を強調する代表的な研究でした。同教授は、『アメリカ著名女性人名録』に掲載された大学卒女性を対象にその出身大学を調査した結果、女性の大学は共学大学に比べて約二倍、各界で優れた業績を残す女性を輩出していることを突きとめました。同教授は女性大学のこのように高いアチーヴァー輩出率の理由として、以下の二つを推察している。すなわち、まず、女性の大学では共学大学に比べ、女性たちが学業・課外活動においてリーダーシップを発揮する機会が多いことであり、さらには、女性大学では、学生たちに対して、伝統的に女性が専攻しないような学問分野を学ぶことを奨励するため、これらが合わさって大学卒業以降のキャリア選択をはるかに広く豊かなものにする、ということでした。
共学の教室内の「冷ややかで人を萎縮させるような雰囲気」
ティッドボール教授の研究が女性大学の新たな存在意義を提起するものであったとすれば、これとは逆に、共学大学における女性の学生の疎外状況に焦点を当てた研究も大きな注目を集めました。ホールとサンドラーの二人の女性研究者の手による一連の研究は、共学大学の教室内での女性の学生がおかれた状況を「冷ややかで人を萎縮させるような雰囲気(Chilly Climate)」ということばで表現しました。自分がクラスの周辺部に追いやられていると感じているとき、あるいは、授業に参加することを期待されておらず、したがって授業に何ら重要な貢献ができないと思われている場合、人は誰でも自身の知的能力を疑い始めます。たとえ同一内容の発言をしたとしても、女性の声に対しては冷ややかな反応が帰ってくる――たとえば、教員が男女によって異なった期待を抱いていることを暗示的にであれ表明したり、女性の学生の学業やキャリアについてのアスピレーションは男性の学生のそれらに比べて重要ではないのだと思わせてしまうような言動など――のであれば、女性の学生の全人的な発達を挫くものになってしまいます。
教育においてジェンダーの作用に敏感であること
男女両性へ同じ教育をあたえれば同じ結果を生むであろうという仮定は、ジェンダーは何ら差を生まない差であるという前提に立ったものです。しかし、私たちはこの世に生を受けたまさにその瞬間から、ジェンダーによって異なった取り扱いを受けています。幼年期に開始され、児童期・青年期を通じ成人期にまで継続されるこのような社会化の過程が、学習に何らの重要な結果をもたらさないと考えることは無理でありましょう。
「ジェンダーは、ある場合にはまったく差異にならない相違であっても、別の場合には大きな差異になることがあるのだから、私たちはジェンダーの働きを絶えず意識し考慮していなければならない」――教育哲学者ジェイン・マーティン教授は、このようにジェンダーの働きを絶えず意識した教育を、ジェンダー・センシティブな教育と呼ぶことを提案します。
ジェンダーが高等教育を考えるにあたってきわめて重要なカテゴリーであるとすれば、私たちは、大学教育の場で、ジェンダーの働きに常に敏感でなければならないはずです。それは、従来の大学教育すべてを、ジェンダーの観点から見直すことであり、カリキュラム・教授法・学習環境のすべてにわたって、健全な懐疑心を持ち続けねばならないことを意味するでありましょう。そして、日本における女性大学の存在は、アメリカ合衆国がそうであったように、ジェンダー・センシティブな教育の実験という意味で、大きな意義を持つものと言えましょう。
〈創価大学教育学部教授〉
キリスト教学校教育 2003年11月号2面