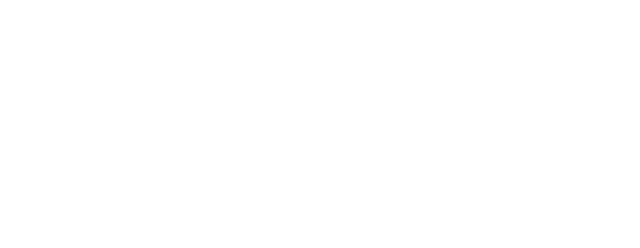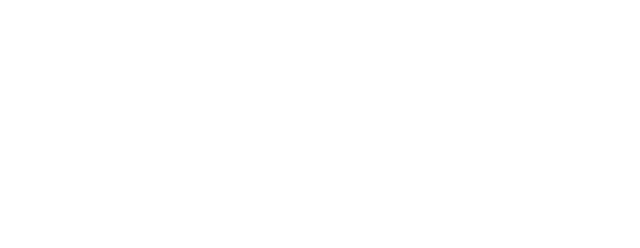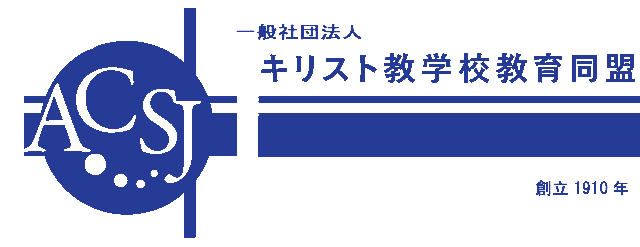キリスト教学校教育バックナンバー
第四八回大学部会研究集会
講演1 ドストエフスキーと戦後文学
-椎名麟三を中心に
-椎名麟三を中心に
斉藤 末弘
「宗教的説教家は、文学の全範囲を喜劇的に処理するのに必要な宗教的高さに到達するであろう」(ゼーレン・キルケゴール『哲学的断片・後書』、鬼頭英一訳)
廃墟の灯火
昭和四十八年三月、椎名麟三は六十一年の生涯を閉じた。三十日、日本基督教団三鷹教会で告別式が行われた。
その時、大江健三郎は次のような弔辞を述べた。
「椎名麟三さん、日ましに私どもにあなたの励ましの光が必要となるでしょう。私どもはあなたを記憶しつずけぬわけにはゆかず、あなたの『ほんとうの自由の光』『ほんとうの救いの光』へ向けて眼をあげつずけぬわけにはゆかぬでしょう。私ども無信仰のものにとってもあなたはいつまでも私どもとともにあります。」
私には、この大江の最後の言葉が忘れられない。かつてジャン・ポール・サルトルが、来日した時、こう言った。「現代を危機として捉えない知識人は、知識人でもなんでもない」と。………終戦直後わが国は「廃墟」だった。衣食住もなく巷に「夜の女」が溢れ、『肉体の門』(田村泰次郎)がベストセラーとなり、永井荷風の『踊り子』がその時代の象徴的な作品となった。つまり私たちは「裸身」で世界の只中に立たざるを得なかった。その時、わが国の知識人たちはドストエフスキーの文学を貪るように読んだ。三島由紀夫から森有正・野間宏に至るまで。……またJ・PサルトルやA・カミユ等、世界の人々が読んだといってもよい。その流行は『戦後の精神的現実』(平田次三郎)であった。従って『焼跡のイエス』(石川淳)や『焼跡の大審問官』(竹山道雄)が出現したのである。
「おまえ(注、イエス・キリスト)はきたのか。この大きな焼け跡にまできたのか。この昨日も今日もない、食を求めて目を血走らせ、ただ生きることに追いかけられて、ほとんど物を考える余裕とてもない大勢の人間のところに、またきたのか。そして、これらの人々に個人の良心を教えようというのか。」(昭和二十三年五月『焼跡の大審問官』竹山道雄)
この竹山の問いは、今も私の中心にある。旧制三高の二年の時、ドストエフスキーに憑かれた野間は、終戦直後、陸軍刑務所から出て来てこう書いた。
「戦争がもたらす不安や苦しみや暗さを、うちから拭い取って、自分自身の歪みや汚れや醜さを正し、下から支えて生かしてくれるようなものが、現代の日本文学には一つもない」(『物語戦後文学史』)と。……
戦争の哀しみを「うちから拭い取って自分自身の歪みや汚れを正し、下から支えて生かしてくれる」ようなものとは、キリスト教以外に当時なかったはずである。従って椎名麟三は、飢えつつも新しいキリスト教的実存主義を目指さなければならなかったのである。
椎名麟三とドストエフスキー
椎名が獄中でニィチェに導かれて、ドストエフスキーに邂逅したのは、昭和十三年、二十七歳の時であった。
「とにかくその『悪霊』という作品は、私をうちのめしたのだ。同時にそれは、人生には究極の解決はないと思っていた私には、思いがけない一つの光だったのである。それは私に、たとえ人生に解決がなくても助けてくれえ!と叫ぶことはできるということを教えてくれたのであった。溺れて死にそうになっているものが、岸に人がいないということがわかっていても、助けてくれえ! と叫び出さずにはおれない、あの叫び声のようにだ。」(『ドストエフスキーと私』)
そしてある時は『未成年』アルカジイの自殺のピストルの不発の音を、またある時は『地下生活者』の歯痛の「呻き」声を、さらに『罪と罰』の酔っ払いマルメラードフ戯言から、ほんとうの「自由」の叫びを、椎名は聴いてしまったのである。
「貧しい人間、孤独な人間、途方に暮れた人間のなかに宿る、この自由への要望、それはどんなことがあっても消し去ることはできないだろう。」(『罪と罰』〈マルメラードフ〉)
ここに野間宏の表現を借りれば、戦後の「下からの改革」を願う第一次戦後派の強いモチーフがあった。模倣から独自の世界を築くまで、十五年の歳月が必要だった。昭和十七年の「ドストエフスキーの作品構成についての瞥見」や、未完小説『祈り』に影響が色濃く出現しているが、戦後では、処女作『深夜の酒宴』(昭二十二)や『永遠なる序章』(同二十三)等にその闘いの痕を見ることができよう。特に昭和二十年代前半の作品は「神への呪詛」がモチーフとなっている。それは共産主義からキリスト教へという邂逅の歴史ともなったのである。この重い問題を集約しているのが『大審問官物語』である。
『大審問官物語』の両義性
『カラマーゾフの兄弟』の次男イヴァン(合理主義者)が、弟アリヨーシャ(ロシア正教徒)に語る十六世紀スペインの詩劇は、言うまでもなくイエスの再臨を「無力」な「囚人」として葬るか、それとも「無力な」「愛」に軍配を上げるか、という問いを読者に投げ掛けている。老大審問官の「唯物的」「合理的」で、徹底的に「悪魔的」論難の果てに、囚人イエスは一言も喋らず次のように応える。
「突然囚人は無言のまま老人に近づいて、九十年の星霜を経た血の気のない唇を静かに接吻した。それが答えの全部だった。老人はぎくりとなった。何だか唇の両端が動いたようだった。」(小沼文彦訳)
椎名はこの「接吻」に、限りない「愛と同意」を、「超越と同時に拒絶」の両義性を見たのでのである。囚人の賢明な「愛」の態度は、あの有名な「姦淫の女」の物語の「この中で罪のないものが石を投げつけるがよい」に重なるものがある。従って作家は、昭和二十五年のクリスマスに「ドストエフスキーに賭けて」洗礼を受けたのであった。
「笑い」から「ユーモア」ヘ
ドストエフスキーは『白痴』完成直前、姪宛にこう書いた。「この世にあくまでも美しい人がただ一人だけあります。それはキリストです。……ただこのことは言っておきますが、キリスト教文学に現れた美しい人物の中で、最も完成されたものは、ドン・キホーテです。」と。……この「白痴」的光源は、イエス・キリストに発し、方法は「ドン・キホーテ」として哀しくもまた、ユーモラスに創造されることになったのである。椎名は、ニーチェから「笑いの聖化」を学び、『重き流れのなかで』(昭和二十二)を書き、暗く重い戦後を乗り越えようとした。そしてキルケゴールの『哲学的断片・後書』を暗記するほど読んで、受洗以後「ユーモア」こそ現代文学の壁を打ち破る武器であることを、主張してやまなかった。
一、「すべての人が実存する限り苦悩すると考える点にユーモアにおける深奥な意義がある」。
二、「世俗的激情の苦しき自己矛盾は個人が相対的テロスに絶対的に関係することによって生ずる」(以上同書)
椎名が、自己の文学的営為の中心に「人格的おかしみとしてのユーモア」を据えたことは,戦後の「笑いよ、起これ」運動とともに注目されよう。これらユーモラスな人間像は名作『美しい女』(昭三十)や、未完小説『西に東に』に至る生涯のテーマともなったのである。
*おことわり
第四八回大学部会研究集会は、九月七日(火)、八日(水)タカクラホテル福岡で開催予定であったが、台風十八号のため中止となった。しかし、講師の先生方は御準備くださったので、講演要旨を掲載することにした。
キリスト教学校教育 2004年12月号2面