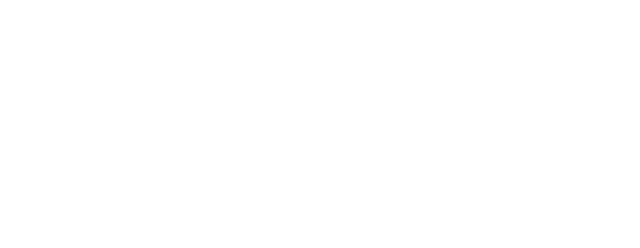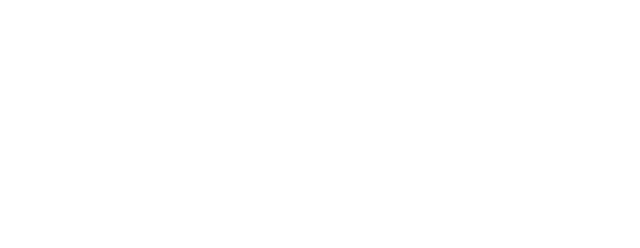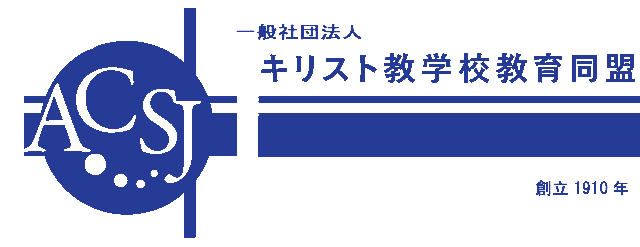キリスト教学校教育バックナンバー
第49回事務職員夏期学校
キリスト教入門特別講義
キ リ ス ト 教 と 文 学
-内村鑑三を通して-
-内村鑑三を通して-
富岡 幸一郎
キリスト教学校教育同盟の特別講演ということで、今日は「キリスト教と文学」という題で話をしてみたいと思います。もちろん、大変おおきなテーマですので、限られたことしかふれられませんが、キリスト教に関心を持つことのひとつの手がかり、入門として文学を通してみることができると思います。
最初に個人的なことを申しますと、私は一九七九年に文芸雑誌の『群像』に、日本の戦後文学の作家である埴谷雄高(はにやゆたか)と三島由紀夫についての評論を応募して佳作となり、以後、主に戦後の作家論や作品論を書いてきました。しかし、一九八八年に『内村鑑三――偉大なる罪人の生涯』という小さな本を書きました。日本の無教会派の創立者であり、キリスト者として近代日本の人々に多大な影響を与えた内村鑑三を通して、はじめてキリスト教、そして聖書と出会ったのです。
それまでもロシアの文学者のドストエフスキーや、戦後派の作家でプロテスタントに入信した椎名麟三の作品などから、キリスト教についてはいくらかの知識がありました。しかし、内村鑑三の著作に接して、自分のキリスト教観が全く狭く、偏見に満ちたものであったことがわかりました。
内村全集を繙きながら、何よりもその言葉の力、エネルギーに圧倒されたのです。文学によって言葉の表現力の深さ、面白さは十分に知っていたわけですが、内村鑑三の言葉はそれとはまた異なる、私自身にとって文字通り「新しい言葉」だったのです。その言葉のひとつひとつに、おそれと戦(おのの)きを体験したといってもいいでしょう。
言葉は人間に与えられた特別の能力です。言葉によって人は人たりえるし、この世界も成立していますが、それはただコミュニケーションの手段ではなく、神から与えられたものだと思います。
私が内村鑑三を通して出会った、「新しい言葉」とは、聖書に記されているイエス・キリストの再臨の言葉です。福音書は、イエスの誕生とその活動、そして十字架上の死を伝えています。イエス・キリストは、しかし三日後に復活したと伝えています。死という絶対の壁がそこで突破されたのです。この死からのよみがえりこそ、キリスト教信仰の根本です。イエス・キリストは、まさに神のみ子であったことを、人々は信じるようになったのです。
しかし、新約聖書が伝えるのはその復活の奇蹟にとどまらないのです。復活したイエスは、四十日間弟子たちと共にあったのですが、その後天に昇られる。イエスが天に上げられ雲に包まれてその姿が見えなくなったとき、残された使徒たちに、御使いが次のような約束を告げます。
「あなたがたから離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる。」
(使徒言行録1・11)
キリストは再びこの地上に来臨される。それは宇宙的な出来事として、将来にかならず起こり、救いはその時に完全に成就するというのです。この「終末」の時を待ち望み、そのことによってこの地上の生命を充実したものとすることができる。キリスト教では、これを終末論といいますが、内村鑑三は近代のキリスト教会があまり積極的に語らなくなった――しかし、聖書にははっきりと記されているこのキリスト再臨の信仰の大切さを再発見したのです。異邦の地にあって、日本人の一人のキリスト信徒として、この初代の教会の人々、パウロたち使徒が真理として信仰したイエス・キリストの再臨、再来を、聖書の最終的な秘義として信じたのです。いや、のみならず、一九一八(大正七)年から一年半にわたって、再臨信仰を日本の各地を巡って伝道します。
内村がどうして再臨信仰に至ったのか、それは彼自身の聖書研究の深まりがあったのはたしかですが、それだけではなく時代と世界の情況が深く関わっていたと思います。つまり、第一次世界大戦という巨大な戦争がヨーロッパ、キリスト教の文明国において起こったことです。それはまさにキリスト教国ばかりでなく、世界の危機でした。そういうなかで、聖書が証しする真理に、あらためて耳を傾けたのです。
同じことは、ほぼ同時期にスイスの牧師であった、カール・バルトにおいても起こりました。バルトもまた千九百年の時をこえて、初代の使徒たちの言葉を改めて聞き直したのです。そして、近代のキリスト教会が語らなくなった終末論の信仰を、生き生きと語り直してみせたのです。バルトの『ロマ書』(一九一九年)という著作がそれです。
内村とバルトという、洋の東西のクリスチャンが、二十世紀の前半に、パウロの信仰と精神を現代へとよみがえらせたのです。
さて、文学の方へ話を移していきたいと思いますが、内村鑑三は先程いいましたように、無教会というキリスト者の集まりを形成しましたが、明治以降の文学者たちにも少なからぬ影響を与えています。正宗白鳥、志賀直哉、有島武郎らは直接に内村と接していますし、その他にも太宰治など、内村に会ったわけでもないのですが、彼の著作を熱心に読んだ文学者がありました。それはやはり内村という信仰者の強烈な個性と、そこから発せられる自己をこえた超越者(神)への信頼からくる、言葉の力によるものだったと思います。
正宗白鳥は自然主義作家として文壇で活躍した人ですが、太平洋戦争後に『内村鑑三――如何に生くべきか――』という評論を書いています。昭和二十四年のことです。そのなかで注目すべきは、内村の再臨信仰について言及している点です。
「私が内村のこれ等の説(再臨・復活)に共鳴しようとすまいと、彼がそれを生存中の大問題としたことに、私は重要な意義を認めようとするのである。如何にして生くべきか、或ひは如何にして死すべきか、それを機縁として私は考へるのである。」
七十歳の正宗白鳥は、若い頃に植村正久牧師から洗礼を受けていますが、内村の信仰にも強い関心をよせていたのです。しかし、敗戦を体験し荒廃のなかにあった戦後の日本のなかで、白鳥はとくにその再臨信仰に重要なものをはじめて見出したのです。
「内村の再臨演説は一時、若い聴衆を感激させたとは云へ、感激した聴衆のうちに、再臨感を持続したものは殆んどなかったであらうと推察される。(中略)キリスト再臨なんか考へるのは、狂的な考へであると見做してゐるらしい。しかし、人間救済のために十字架に上りしキリストを信じる以上は、再臨を信じるのはあたり前の事で、奇矯でも何でもないのである。根本の一つを信ずれば聖書全体がそのまま信じ得られるのである。(中略)今日のような時世こそ、キリスト再臨は最も期待されるべきである。」
既成の社会秩序が崩壊し、混乱のうちにあった敗戦後の日本にあって、正宗白鳥という一人の文学者は、内村の再臨信仰にあるリアリティを感じたのでしょう。
「如何にして生くべきか、或ひは如何にして死すべきか」――これは文学の究極的なテーマでもあります。正宗白鳥は、自分が文学者として考えつづけてきたテーマの根本が、内村鑑三というキリスト者の魂の内部にあったのを改めて発見したのだと思います。
宗教と文学は、このように人間の生と死、その存在をめぐって、きわめて共通した場所に立っています。それはときに背反したり、反発したりもしますが、この世界の現実に真剣に目を向けようとすれば、深く関わり合うものです。
キリスト信徒は、日本では少数者です。マイノリティです。しかし、近代以降の日本文学には、キリスト教は思いの他に深い影響を与えています。そこには西洋を学ぶことで、近代化を押しすすめてきた近代日本の事情もありますが、たとえば北村透谷のようにわずか二十五歳で亡くなった文学者のうちに、キリスト教、聖書がもたらしたおおきな精神的力があります。ここで紹介することはできませんが、クエーカーの平和主義の運動などにも透谷は関わっています。そして、旧約聖書のヨブ記などを用いて、根源的な平和とは何であるかを説いています。
これは戦後の文学者にも当てはまるでしょう。カトリックでは遠藤周作が有名ですが、私はプロテスタントの信仰を得た椎名麟三の名前をとくにあげておきたいと思います。戦前にマルクス主義、共産主義の思想に関わった椎名麟三は、戦後の廃墟のなかで作品を書きはじめますが、ニヒリズム(虚無主義)に陥り自殺を考えたといいます。しかし、昭和二十五年に洗礼を受けて、あらたに生きる途を見出すのです。椎名文学は決して説教的な文学ではありません。むしろ、人間の絶望や矛盾を正面きって描いています。しかし、ある独特のユーモアもあるのです。それは人間はつねに神の恵みの下にあり、その恩恵の光のなかで生きることができるという信仰によるものです。
最近、イスラム原理主義という用語がよく出てきますが、キリスト教もふくめて、いや宗教だけではなく、人間と社会のさまざまな場面で、自分の信ずる者以外を認めないという悪しき原理主義が生じます。椎名麟三は、それを人間が「これは絶対にほんとうのものだ」と思い込む、そのことであるといいます。「ほんとうのもの」と一たび思い込むことは、他者を認めず、自分を絶対化することです。しかし、イエス・キリストが示されたことは、われわれのそういう「ほんとうのもの」をいう思い込みから自由になる道である、と椎名はいいます。そこに赦しがあり、ユーモアが生じます。キリスト教は、こういう作家の作品を通してふれることもできるでしょう。学校教育の場においても、キリスト教を押しつけるのではなく、文学作品などの素晴らしい言葉の世界から入っていくことができます。そこで、きっと「新しい言葉」とのそれぞれの出会いがあると確信しています。
〈関東学院大学教授、文芸評論家〉
キリスト教学校教育 2005年9月号3面