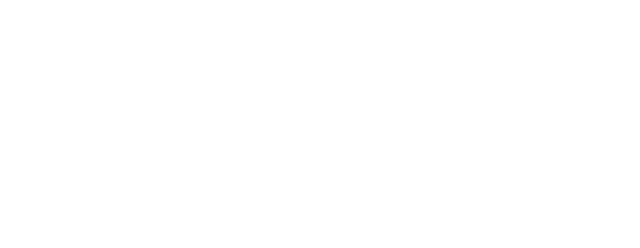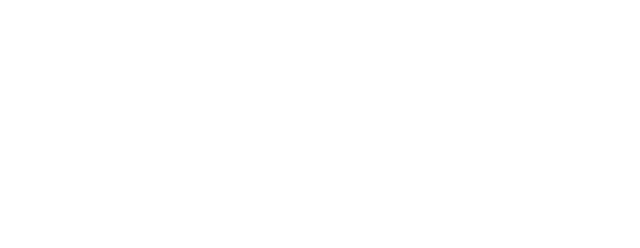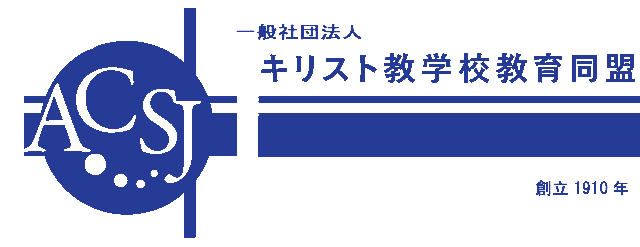キリスト教学校教育バックナンバー
キリスト教入門特別講義
キリスト教学校の苦難の歴史
気賀 健生
与えられた「キリスト教と歴史」の題のもとで、ここでは専ら「キリスト教学校の歴史」について考えよう。
明治以降のキリスト教学校の歴史は、そのまま日本におけるキリスト教およびキリスト教会が経験した歴史であった。政府の政治的圧力と制限のもとで、ある時はこれと闘い、ある時は屈従し、隠忍自重しつつ、何をどのように勝ち取っていったか。ここでは主として次の二つの事象について考察しよう。
一つは一八九九年の「訓令十二号」事件。これは直接キリスト教学校を標的とした政策で、キリスト教学校にとっては、死活に関わる重要な歴史的事件であった。その被害と対応のあり方について考える。
もう一つは、昭和期における思想統制・弾圧に対して、キリスト教学校は如何に対処したかについて考える。そして現在、それらの「外圧」をくぐりぬけてきたキリスト教学校は、その「使命(ミッション)」を如何にはたしているか、を考えてみよう。
徳川封建体制が崩壊し、近代日本の統一を緊急命題として登場した明治政府は、天皇制をもってその支配原理とした。それが天皇制絶対主義の論理的完成としての帝国憲法制定であった。憲法制定会議議長伊藤博文は「本邦に於ては貴族及人民の参政権は天皇陛下の付与せらるるものなり、決して貴族人民の固有の権に非ざるなり」と、明確に主権在民を否定し「今憲法の制定せらるるに於ては、まず我国の機軸は何なりやを確定せざるべからず……我国に在て機軸とすべきは独り皇室あるのみ」と宣言した。伊藤はここで、政治の機軸としての宗教を持たない日本に於いては、天皇を以って之に代替する他はない、と説いているが、その論理の延長線上にある問題は、機軸としての天皇権力の、やがては神化にまで至るべき、国家論理の国民教育レベルにおける確立であった。そして、そうすることによってこそ「神聖にして侵すべからざる」天皇の仁慈と恩恵がうたわれることとなり、またこれに対する国民の感恩と随順が、最高の道徳として強調されることとなったのである。
このような文脈の中で教育勅語は如何に位置づけられたか。教育勅語は当然に、神格天皇を「機軸」とする体系的縦編成社会の倫理規範となったのであるが、それが「国家倫理」であったことによって、倫理は著しく国家目的に適合的な人間形成をその価値基準とすることになり、天皇制絶対主義を国民の側から支えるという機能を果たすこととなった。このように教育勅語が天皇制国家の論理を基礎づける倫理規範であった以上、国民教育の課題が、国民を人格として尊重し、その市民的成長を育成するのではなく、天皇を頂点とする国家形成の目的に適合的な人間像の養成にあったことも自明であった。
以上で明らかなように、天皇制をいうものは実は明治維新以後「創り出された」イデオロギーだったのである。そしてこの過程で、切り捨てられるべき人権論、人格主義、自由主義などと共に、キリスト教は有害な価値体系として否定されなければならなかった。これ以後、キリスト教は反倫理思想として迫害の対象となっていったのである。
こうして、天皇制国家権力による干渉が、キリスト教およびキリスト教学校に向けられたのが、キリスト教学校における宗教教育および儀式の禁止を内容とする「文部省訓令十二号」事件であった。この訓令の出されたのが一八九九(明治三十二)年八月三日であったという事実が、訓令の目的を如実に物語っている。即ち一八九九年、懸案久しきに及んだ条約改正の治外法権撤廃が実現され、八月四日から外国人の内地雑居の実施が予定されていた。訓令十二号はこの新事態に備えたものであった。即ちこれによって外国人宣教師が多数来日し、日本人と雑居し、キリスト教の宣教とその学校教育が発展して、折角確立した教育勅語を中心とする天皇制国家の教育方針が乱されることを恐れ、キリスト教学校からキリスト教教育を放遂して、文部省完全統括のもとに、全国の国公私立学校を置こうとしたものであった。即ちキリスト教学校におけるキリスト教教育およびキリスト教儀式(礼拝)を禁止する。もしこれらを行う場合には、上級学校進学資格および徴兵延期の特典を剥奪して各種学校とみなす、というものであった。
このような事態に各キリスト教学校はどう対処したか。土肥昭夫氏の説に従って見てゆこう(塩野和夫「近代天皇制とキリスト教学校」西南学院大学論集)。
①訓令とキリスト教主義教育は両立しないと判断し廃校に踏み切った事例-私立桜井小学校
②既存の文部省令による学校では特権剥奪を覚悟してキリスト教教育を堅持するが、同等の教育を行う普通学校を新たに設立してここでは訓令に従う―明治学院、青山学院
③訓令とキリスト教教育の両立を唱えたが実現せず、②の方法を選んだ事例―同志社
④訓令に従いキリスト教教育や儀式を学校で行わず特権を守ったが隣接する学校の教会や寄宿舎でこれを行い、生徒には出席を義務づけた事例―立教中学校
⑤文部省令による学校を存続させるため、キリスト教学校であることをやめた事例―東洋英和学校中学部(後の麻布中学校)
⑥キリスト教教育や礼拝を堅持して、各種学校と認定された事例―横浜共立女学校、等
この事態に対してキリスト教学校は共同してその権利を主張し、訓令を批判した。即ち「日本帝国憲法は信教の自由を与ふ」のであるから「宗教教育並に宗教的儀式を禁止せる文部省のこの態度は、子弟の教育を選定する父兄の自由を検束するものにして帝国憲法の精神に反戻する」と意見書を公にした。そして文部省を訪問し、陳情を重ね、訓令十二号の撤廃を求めたが、文部省の門は堅かった。しかし、反対運動は意外に早く当面の成果を得た。二年後から順次「法令の規定ある学校」に準ずる取り扱いを受け、上級学校への受験資格や徴兵猶予の特権を得た。キリスト教界の反対や欧米諸国からの反発が予想外に強かったため、訓令を厳格に適用出来なかったためであるが、しかし撤去もしなかった。
その結果訓令十二号は、なんと一九四五年までキリスト教学校を束縛し続けた。事例②③④のケースでは、各学校はキリスト教教育をそれぞれ巧みな手段で堅持したが、同時に天皇制国家の枠組みから逃れることもできなかった。それが後に昭和期になって「寄附行為」改変につながるのである。しかし、訓令十二号がもたらした困難な状況は、キリスト教学校の間に連帯感を生み、一九一〇年の基督教教育同盟会設立の契機となったといえよう。
それから約半世紀、昭和期における思想統制・弾圧は記憶に新しい。ここでは、各キリスト教学校が、場合によっては廃校という危機に直面して、それぞれの建学の精神の拠り所である「寄附行為」を改訂・後退してまで、その存続をはからざるを得なかった状況を、青山学院を例として省みておこう。
「青山学院の教育は永久に基督教主義にして其教義の標準はメソジスト・エピスコパル教会条例の信仰個条に拠るべきものとす」
これは一九〇六年の建学以来、連綿と守り通して来た「青山学院憲法」であった。これが一九四二年次のような痛恨の憲法改訂に至る。
「青山学院は教育勅語の聖旨を奉戴して皇国の負荷に任すへき人物を練成し基督教精神を採りて之が陶冶を計るその大綱は日本基督教団の示す所に拠る」
ここでは「永久に基督教主義」を宣言した青山学院の教育目標が「教育勅語の聖旨を奉戴」することとなり、「皇国の負荷に任すへき人物」を陶冶する手段として「基督教精神を採」ることで、僅かに建学理念のアイデンティティーが表明されるに至ったのであった。状況は他のキリスト教学校においても同様であった。関東学院では一九四〇年に「本学院の教育は教育勅語の聖旨を奉戴し之を実現する為に基督教により人物を養成し」と、「基督教主義に基く教育」が教育勅語にとって替えられ、明治学院でも「基督教主義の教育を施す」ために建てられた学校が「教育に関する勅語の趣旨を奉戴」することとなった。
このような痛ましい歴史は、一九三〇年代から四一年の日米開戦に至る、日本の軍国化と思想の暗い谷間への過程と共にすすめられていった。満州事変、上海事変から始まった軍部の暴走は、一九三七年、日中戦争に突入、国家総動員法に続いて大政翼賛会が発足した一九四〇年には、「紀元二六〇〇年」を謳って皇国化が決定的となる。文部省には思想局・教学局が置かれ「青少年に賜りたる勅語」による思想の強制的皇国化は、一九四〇年の新体制運動へと方向付けられ、一九四一年の日米開戦に至る。戦局の進展と共に「皇国民の練成」に教育目標が収斂され、緑美しい各学校のキャンパスにも、軍国主義の土足が踏み込んでくる。「寄附行為」改訂による痛恨の建学理念の後退は、このような過程の中のことであった。
戦後一九六七年、日本基督教団は総会議長鈴木正久牧師の名で所謂「戦争責任告白」を発表した。「まことにわたくしどもの祖国が罪を犯したとき、わたくしどもの教会もまたその罪におちいりました。わたくしどもは“見張り”の使命をないがしろにしました。心の痛みをもって、この罪を懺悔し、主にゆるしを」願うこの告白は、そのままキリスト教学校にあてはまる懺悔であった。どのような理由があろうとも、時代と政治の圧力に抵抗しきれず、教育勅語を受け入れ、天皇制の魔術に操られ、建学の理念を放棄した罪は、心の深い痛みであり、戦後しばしば唱えられた「一億総懺悔」などという訳の解らないキャッチフレーズでなく、それぞれの否定すべき歴史、継承すべき歴史の精算を問い直し、各学校における建学理念の再構築をはかるものであった。
今日、以上に指摘したような「外圧」は最早ない。外からの圧力は、それがどのように強くあろうとも、内側の力によって闘い、耐えることが可能であるが、内側からの建学理念の忘却、腐敗、またはこれを薄めてゆく傾向が、万が一見られるとするならば、これは致命的である。現代の情報化・科学化社会の中にあって、学校教育において「手段」が「目的化」してはいないであろうか。コンピューターの時代という。コンピューター文化も文化である。しかしここからは「心」は見えてこない。手段が目的化するとき、「心」は見失われる。青山学院第二代院長本多庸一は「願わくは神の恵により、吾輩の学校よりは、“MAN”(人格・人物)を出さしめよ」と祈った。この祈りは今もそれぞれのキリスト教学校にあって共通の祈りであろう。ミッション・スクールにおけるミッション(使命)を今ひとり一人が胸に刻んで、創立者の意思に立ち返る時が来ている。そこで、「キリスト教学校で働くとは?」
〈青山学院大学名誉教授〉
キリスト教学校教育 2006年9月号3面